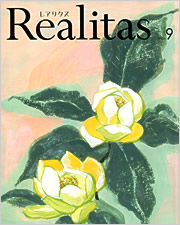アルティザンの仕事場 【虎斑竹】(高知県・須崎市)
ARTISAN
日本で唯一、そこだけに産する"ミラクルバンブー"の里がある。
虎皮の斑があるミラクルバンブー
高知県須崎市安和。三方を山に囲まれ、一方は須崎湾、遠く太平洋を望むわずか1.5キロ間口の谷間の里にしか育たない特殊な竹がある。「土佐虎斑竹(とらふだけ)」。
表面に虎皮の模様があるこの珍しい竹を産する里は、いまでこそ国道が通り高知市から四万十市へと車が行き交う土地だが、かつては人の往来には不便な交通の難所であった。
その自然環境が土佐藩の時代には年貢として献上されたという特産の「虎斑竹」を現在にまで守るという結果を生んだ。
竹材商だった創業者が明治時代にこの貴重な竹と出会い、二代目がこの地で「竹虎」の屋号を掲げた竹材メーカーは、いま四代目によって、竹の持つ大きな可能性に挑んでいる。
日本人とその文化を育んだ竹
竹は、昔から日本各地に広く分布し、日本人の暮らしに密着したさまざまなものに利用されてきた。日本人と竹の関わりの歴史は古い。縄文時代の遺跡からも竹を素材としたものが出土している。農漁業でも、竹はごく身近にあって、軽くて加工性の高い素材として、用途に合わせて自分で編むだけでなく、職人に注文して使いやすい形や大きさにした竹籠をいくつも使用していた。
また、日本家屋には至るところに竹が使われていた。土壁には竹を芯に塗り込め、寒さ、暑さ、湿気を調整するなど、日本の気候に適した素材として活用されてきた。あの日本の代表的な建築である「桂離宮」も、屋根裏、窓、縁側など、なんと家屋材料の半分以上に竹を使っている「竹の家」なのだ。
笊や籠、花器などの日用品から、茶道や華道の道具、笛や尺八などの楽器、竹刀や弓などの武道具...と、しなやかでかつ強く、多岐にわたる用途に活用できる竹は、まさに自然からの恵みであり、日本文化の伝承や人々の暮らしに欠かせない素材だった。
しかし、いまでは現代人の生活の中から竹に接する機会がどんどん少なくなってきている事も事実である。プラスチックなどの素材の登場や、なによりも身近な自然の素材を活かすという生活式からの変化が大きな要因となった。
・右写真
虎斑竹を細かく割いて、薄く削いだものをきっちりと編んで作った花籠には、楚々とした花を生けたい。
・左写真
竹藪の急な坂道をひょういひょいと登って竹を吟味する四代目。

竹は、分類の仕方や種類の数え方には諸説あるそうだが、一般には国内にある竹は約600種に及ぶとされている。その多様さには驚かされる。代表的なのは、真竹(まだけ)、淡竹(はちく)、孟宗竹(もうそうちく)などだが、そんな竹の中で、日本の高知県須崎市のある土地だけで採取できる珍しい竹があるという。「虎斑竹」。
かつては土佐藩へ年貢として献上されていた銘竹と出会った創業者以来、この竹の製造を専業として四代にわたって竹材業を営む「竹虎」を、高知に訪ねた。
虎皮の斑がある不思議な竹
「竹虎」四代目の山岸義浩さんが、首にタオルを巻き、前掛けと作務衣姿で登場した。よく似合い、様になっている。
「虎竹は、まっこと不思議な竹ながぞね。間口が1.5キロしかない、ここ須崎市安和という里の谷間にしか成育せんがです」
開口一番、高知の訛りそのままの語りがとても新鮮だ。
「虎斑竹」は、三方の山に囲まれ、残りが海岸線というこの一角だけにしか見られないとても珍しい竹なのである。
虎斑竹(虎竹)は、淡竹の仲間だが、表面に虎の皮に似た模様が入っているところからこう呼ばれる。正式には「土佐虎斑竹」。高知県出身の世界的植物学者、牧野富太郎博士がこの不思議な竹の命名者だ。1916(大正5年)のこと。
「はちくの変種にして、高知県高岡郡新正村大字安和に産す。(現在の須崎市安和)凡の形状淡竹に等しきも、表面に多数の茶褐色なる虎斑状斑紋を有す。余は明治45年4月自園に移植し、目下試作中なるも未だ成績を見るを得ず。」と記している。
「実はいままで何度か移植を試みたことがあるんですが。他の地域ではなぜか虎の模様が表れずに、数年経つと普通の竹になってしまう」
なぜこの地でしか成育しないのか、大学の調査でも解明されていない。
「先日、ある大学の先生と話す機会がありました。その先生は『ストレスが一つの原因ではないろうか?』と、そんなふうに言われるがです」
山岸さんには、そう言われると思い当たる節がある。この里の山々は岩が多く決して肥沃な土地ではない。その硬い岩盤をぬうようにして樹木が根を張る。これは竹にとっても、暮らしやすい環境ではないのかもしれない。
「先生がいうもう一つの要因が潮風です。これは山の職人さんも言っていたことですが、植物にとって塩分は生育を阻害するもの。また、南国土佐といわれる土地だが、昔は雪合戦できるほど雪も降り寒さも厳しかった。そうしたもろもろが、竹に試練を与え、それによって虎模様が生まれるのではと」
・右写真
袖垣作り。あらかじめ組んでいた孟宗竹の柱に細く割いた虎斑竹を巻きつけ、この後、やはり虎斑竹を組み合わせて作った板状のヒシギをはめ込む。
竹の節の部分に残っている枝の付け根を一本一本、鋸で切り取っていく。根気のいる作業だ。700度に温められた炉に切り出した虎斑竹を潜らせて竹の油を抜いていく。
次は油抜きで個性的な模様が出てきた竹を、熱く待っているうちに「ため木」と呼ばれる厚めの板に穴が開いた道具に通し、竹の曲がりを矯正しまっすぐにしていく。
縁台作り。座となるところに細目の黒竹をカズラで組みながら仕上げていく。涼しげでおしゃれな作品は、折りたたみ式になっていて持ち運びにも便利にできている。大・中・小がある。
・左写真
事務所の隣の工場では山のように虎斑竹が立てかけられている。その脇には袖垣や縁台などの大物の作品が無造作に置かれ、出荷を待っている。

「竹虎」の創業は、明治27年。大阪で創業したが、初代は全国で良質の竹材を探すうちに、この不思議な竹と出会う。幾度かこの土地を訪れた初代は結局、安和の山主の娘と結婚する。その初代から数えて山岸さんは、四代目である。
これまで英国のBBCのほか、国内外から多くの研究者も訪れている。虎斑竹の発生する理由は科学的にはまだきちんと解明されてはいない。しかし、山岸さんはいま謎の究明に一歩近づいた気がしているそうだ。
竹に命を吹き込む、技
普通、竹という素材から思い浮かぶ色とは異なる濃い茶褐色の虎斑竹が、工場内の壁いっぱいに立てかけられている。1年分を冬の間に切り出し、材料として置いておくのだ。油抜きという作業を見せてもらった。
製竹作業は4~5人がチームを組んで行う。まず。山から運ばれた竹の「目払い」。竹には、枝の付け根部分が残っている。これを鉈で払うと竹の表皮も削られてしまう。虎斑竹は、表皮の虎模様が命なので、鉈ではなく、鋸で付け根に切り込みを入れて一本一本丁寧にとっていく。ガスバーナーを使った炉に、この竹を潜らせていく。温度は700度。次に竹自身から出る油分で磨くと、それまではっきりしなかった虎の模様が明確に浮き出してくる。一本、一本それぞれ個性的な模様である。
さらに、その個性を最大限に活かすため、熟練した職人の手で矯正される。テコの原理を利用した昔からの道具である「ため木」を使い、油抜きをした熱を利用しながら、節々をまっすぐに矯正していく。これがさまざまな虎竹の製品に生まれ変わるのだ。
別のところでは、職人が虎竹の袖垣を作っている。日本の庭園などでたまにみかける垣根である。細く割った虎斑竹を。太い孟宗竹の芯に巻きつけて作る。竹の節を少しずつズラして模様を作り上げていく。細かな職人仕事である。
竹籠の製作も細かな手技の仕事だ。細く割った竹の皮を、わずか2ミリの厚さに割り、さらにそれを1ミリの厚さにして、編むというより、組んでいく。
・右写真
白竹を編んで作った白竹三段弁当箱や虎斑竹のピクニックバスケット。そして薄く漆をかけた籠。どれもたけ息がでるほど職人の技が光っている。
虎斑竹を細く割いて、薄く削る。それに熱を加えて曲げたりしながら編むと、虎斑竹のランチボックスが出来上がる。作っているのは四代目山岸義浩さんの弟の龍二さん。
・左写真
精巧な竹のカマキリは今にも動き出しそう。このほかにもさまざまな昆虫や動物が事務所横のショップには飾ってある。愛好家が多い耳かきは、これを使うと竹林を吹き抜ける風の音が聞こえそう。竹のワインクーラーは花入れにも。

かつては60人近くの職人を抱えていた時期もあったが、いまでは、日本各地に職人のいわばネットワークを持っている。こうした、技の優れた職人たちとは先代先々代からの付き合いである。何十年も竹細工を編んでいるという人たちだ。職人にとって一日に何個もつくるという作業を通じて、技に習熟する時期がなによりも必要だ。最近では、興味を持って仕事を始めた若い人もいるが、何よりもスピードが違う。そうした熟練の技を積み上げた職人はどんどん少なくなっている。職人の減少は、「竹を扱う人間で竹虎を知らない人間はいないと思う」という山岸さんの危惧する大きな問題である。
ヒーリングスポット、竹林にて
近くにある虎竹の竹林に案内してもらう。工場のすぐ近く、四国の遍路道でもあるという山道。その急な勾配の坂道を、山岸さんはスイスイと登っていく。きれいに管理された竹林には、人の心を癒す働きがある。立ち止まった竹林の中、風の音が澄んで聞こえる。
「どうも日本人のDNAに合致しているのではないかと思うんです。竹林に入って気持ちが悪いという人はいない」
竹との接触が少ない都会からの若者たちを時々ここに連れてくる。彼らは、すぐ竹林のすばらしさに魅了される。
急勾配の細い山道。竹を伐りだして運ぶ道だ。水を含んで重い竹を伐ったり、担いだりする作業は大変な重労働だ。間引きしながら、一本、一本、目で確認して色付きのよい竹を伐り出す。1月から3月頃にかけて、切り出した竹の選別作業が始まる。太さごとに、用途別に選別され、結わえ直し、保管場所へ運ばれる。竹は品質維持のために、旬の時しか伐採されないので、この時期に1年分の材料が山から運び出されるのだ。
竹の文化を未来へつなげる
山岸さんは30年前、全寮制の中学、高校から大阪の大学に進学して10年ぶりに仕事をするため、この地に戻ってきた。
「夜になったら真っ暗で、カエルの鳴き声だけが煩いくらいに聞こえてくる、こんな竹しかないところに明日があるとはどうしても信じられなかったです」
しかし、その迷いもある時、吹っ切れた。四代目としてこの虎斑竹に自分を賭け、竹をつくり続ける職人たちのために日本人が忘れかけている竹の良さを世の中に伝えようと一念発起する。そして、この四国の片田舎から、そんな思いを発信するのに格好なツールがインターネット
だった。
「自分たちでは当たり前、いわなくても見ればわかってくれると思いよったこともありました。けんど、違うがぜよ。いわんと誰も知ってくれませんちや。知らないということは、その価値が伝わらないということですろう。こんなにエイものやのに、どうして誰も買わんがやろうか?デパートに売り出しに行き始めた頃、都会の人が虎竹を見て、なんの反応も示さないのが不思議でしょうがなかったです。こんな珍しい竹が他にあるやろうか?都会にはなんでもあるので本当にそう思ったこともあったがです。でも、違うちょった。いまの日本人は竹を知らんだけだったん
やった」
山岸さんは、30年以上続けるというブログでそんな思いを土佐訛りたっぷりの語り言葉で吐露している。
「我々のような小さな組織にとってネットは大きな武器でした。」
1997年からインターネットでの発信を始め、さまざまなネット上の賞も受けてきた。その結果、マスコミの取材も受けるようになった。
これまで一貫して山岸さんは「21世紀は竹の時代」と言い続けてきた。
竹は筍から20数メートルの親竹に成長するのに、わずか3か月しかかからない。その驚異的な成長力、そして、たった3年で製品に利用できる継続利用可能な唯一の天然資源という観点からだ。このほか、竹の抗菌・消臭などの機能性、食品利用、竹繊維などの新素材を含めるとほとんど無限の可能性を秘めているエコな素材でもある。
社屋の前には、祖父の二代目義浩氏が石碑に刻んだ言葉がある。
「竹の子の、また竹の子の、竹の子の子の子の末も茂るめでたさ」
いま、その言葉のとおり、竹の仕事を未来までつないでいけると、四代目山岸さんは自信を深めている。
・右写真
店頭で竹踏み用に割いた竹を干す。
ショップの壁に掛けられている竹工芸家、宮川征甫氏の作品の一部。薄く切り取った竹の皮をモザイクのように張り込んで作る。祖父の友人でもあった。
・左写真
タオル、長靴、作務衣に藍染めの前掛け。なんとも様になっている山岸さん。
祖父の「竹の子の、また竹の子の...」の石碑。
(雑誌「Realitas Vol.9」より転載)