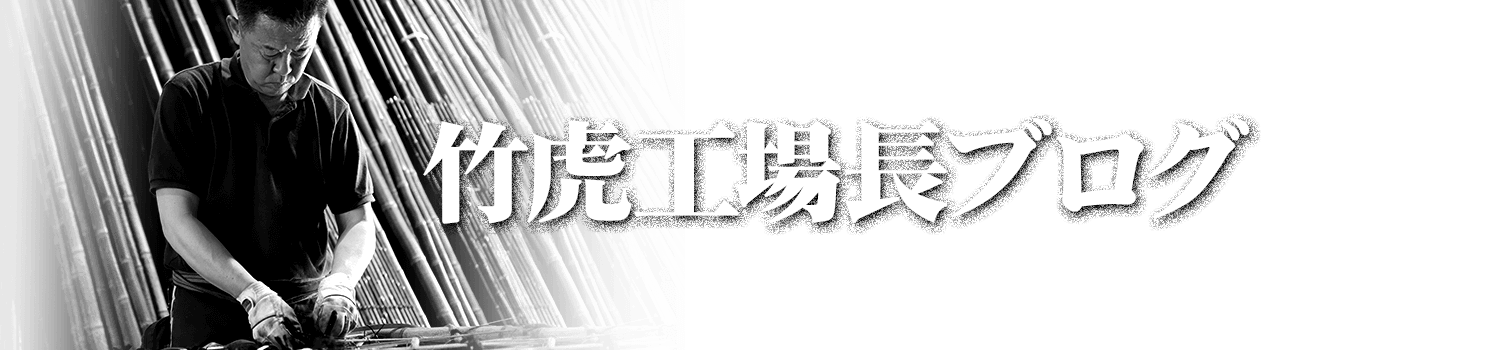竹には表皮部分に固いガラス質の皮があり、それが竹独特の艶となったり、虎斑竹や黒竹のように、その皮部分に色や模様がついている竹では、その表皮部分がその竹ならではの色合いを出しています。
竹細工での「磨く」ということは、その表皮部分を磨き包丁と呼ばれる湾曲した刃物で薄くそぎ落としていくことを言います。青竹や白竹では表皮の傷を削りとったり、乾燥を早めたり、経年変化が早くなることなどから、磨き加工をすることがあります。
また染色をする場合でも、表皮のつるつるした部分には染料がつきにくく、その表皮を剥いでおくと、その内側の繊維に染料が染みこみやすくなるため、色が付きやすくなるのです。
磨く竹は1~2日ほど水に浸けておき、表皮を柔らかくしておきます。そして節の出っ張った部分を竹割り包丁で削り取る節くりと呼ばれる作業で節の出っ張りを削っておきます。
竹をしっかりと固定するか、足などでしっかりと動かないようにはさんで磨き包丁で表皮部分を長く削っていくのですが、包丁を強く当てると傷になったり、節の部分で包丁が跳ねて、傷になったりすると、ヒゴにした時に折れやすくなるので、注意しながらの作業です。
なんでもそうですが、こういった最初の作業が、出来上がりの良し悪しを大きく左右するものです。この磨き包丁から籠作りは始まっているのです。

虎竹は秋から冬にかけてが伐採時期です。今の時期は山から下してきた竹を工場内に取り込んで、油抜きをし、あるいはそれと同時に内装材などにも使えるように真っ直ぐに矯正する製竹作業が本格化しています。
自分が入社したころは、職人さんも数十名もいて、それこそ一年中ひっきりなしに油抜きや矯正作業をして、虎竹を製品として出荷するために製竹作業をしていました。その中で一緒に作業をすることで、仕事を体に覚えさせることができたように思います。
見よう見まねでやることは誰でもできますが、ある程度の量や質をこなさないと見えてこない、わからない本当の技術というのは間違いなくあります。教えてもらっても、聞いてもわからなかったことに気がついて初めて、その作業が本当の意味でわかってくると思うのです。
もちろん、竹は1本1本違うので、それに合わせての作業にもなり、いつまでたっても完璧と思えることやすべて満足のいく仕事というのはできないものです。
今年も製竹された虎竹が、少しずつではありますが出荷されています。割り剥ぎされて籠に生まれ変わるのか、内装材として店舗や施設のアクセントとなってくれるのか、行先は様々ですが、虎竹の里からここにしかない虎竹をこうして発信し続けていけることは、ありがたいことだと思うのです。

昔から天日干し用のかごとして広く愛用されてきたのがえびら(竹編み平かご)と呼ばれるかごです。しらさやじゃこなどの海産物をはじめ、大根やお芋などの農産物を干したり、梅干しの土用干し用に最適なかごとして、今も重宝されています。
15mmほどの幅に割った孟宗竹のヒゴを網代に編み、それを杉板の枠に挟み込んで、しっかりと強度ももたせています。食べ物を乗せるかごですので、杉板も出来るだけ節の無い、赤目の少ない物を選んで、カンナで表面を綺麗に加工して使っています。
いつもお世話になっている製材所にたくさんある杉板の中でも、こちらの希望の厚さ、節の無さ、色目などをクリアした杉板はそう多くありません。そんな材が出た時に選り分けてもらっておいた杉板には、こうして竹虎(株)山岸竹材店の「山岸」という文字が書かれてあり、えびらの材料としての出番を待ってくれているのです。